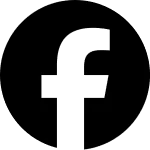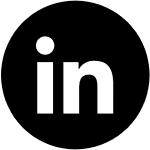2023-03-27
Special Contentsカルチャーモデル醸成へのプロセス #3 後編組織の未来をひらく、創発アプローチとは?
創発を生み出すために必要なこと
組織も個人も成長のプロセスは似ている
前回、組織変容のための5つのステージについてお聞きしました。私自身、レッドに近い組織やアンバー、オレンジ、グリーンなどを経て、現在は個人事業主として、プロジェクトごとにさまざまな方たちとチームを組んで仕事をしています。ティールとまではいかないまでも、あまりストレスを感じることなく仕事ができているように思います。
AKI 僕自身も、現在はひとり起業家として活動していますが、かなり理想に近い働き方ができています。それは、僕自身や麻都佳さんがそうであるように、さまざまな組織を経験しながら、進化の段階をステップバイステップで進んできたからでしょうね。なぜなら、『ティール組織』のフレデリック・ラルーも言っているように、アンバーからティールへ、一足飛びに進化することはできないからです。つまり、ひとつ前の段階を「超えて、かつ含む」ことでしか成長を促すことはできないのです。
実はこうした考え方は、組織のみならず、個人の成長段階とも見事に相関しています。『なぜ人と組織は変われないのか』の著者として知られるハーバード大学のロバート・キーガンが提唱する、「成人発達理論」がまさにそうです。
(図1)はキーガンの成人発達理論を図式化したものですが、人には3つの発達段階があって、自己中心型マインドから、環境順応型マインド、自己主導型マインドを経て、自己変容型マインドへと到達するのだという。色分けしたように、自己中心型知性はレッド、環境順応型マインドはアンバー、自己主導型マインドはオレンジ、そして自己変容型マインドはグリーンやティールに対応しています。
R.キーガン 「大人のマインドの発達段階」

- 図1 個人変容に関する基礎理論〜キーガン「成人発達理論」
この図にあるように、専門性や自分自身の明確な判断基軸を持つ人(オレンジ:自己主導型マインド)しか、次の段階の自己変容型マインド(グリーン)を身につけることはできません。オレンジの人がそうであるように自分自身の価値軸を持っていながらも、それを絶対的なものとせずに、他者の価値軸も受容しつつ第三の道を切り拓いていくのが自己変容型マインドの姿というわけです。一方、日本企業に勤めている多くの人はアンバーの環境順応型で、明確な判断基軸を持っておらず、基本的に組織や上司に従わざるを得なかったりする。そうなると、社内では良くても、いったん会社の外に出るとほとんど通用しません。そういう人たちは、いきなりグリーンに飛ぶことはできないんですね。
もっとも、キーガンが指摘しているように、オレンジには35%、グリーンに至っては1%の人しか到達できないという。残酷なようですが、ほとんどの人はその途中で成長が止まってしまうという調査結果ですね。ただ僕自身は、個人の力でグリーンに到達することは難しくても、組織の進化プロセスをうまく活用しながら、組織との相互作用で自身も成長していくことはできると思っています。
4象限の「らしんばん」を使った創発アプローチ
現状のKnowledge Baseは、オレンジの自己主導型マインドの方が多い印象はありますね。
AKI 経営者の坂本さんは特に優れたオレンジの人という印象があって、どんなことがあってもゆるぎない信念を持って闘い抜けるリーダーだと思います。にもかかわらず、リゾーム状の組織をめざす、つまりティール組織をめざすということはどういうことなのか。それはやはり、これからの時代環境の中で、そこをめざさなければ組織の持続的な成長と発展はあり得ない、という経営者としての判断があってのことだと思います。そのためには、まずは自分自身が自己変容型に変わらなければならないと、覚悟を決めたのでしょう。その本気度は、これまでの対話を通じてヒシヒシと伝わってきます。
確かに、ここまでの坂本さんとの対話、さらには部門責任者の佐々木俊也さん、佐々木皓也さんとの対話を通じて、組織をより良く成長させていきたいという切実な想いを感じてきました。
そうしたなか、今後、AKIさんの創発的アプローチはどのように進んでいくのでしょうか。
AKI 僕は支援の下敷きとして「らしんばん〜要素還元から統合的思考へ」(図2)というマップを採用しています。ここまでの議論は、この図の4象限の左上、「在り方(パーパス)」の段階でした。ここを起点にして、徐々に「物語(戦略)」へ移行していきます。

- 図2 【らしんばん】〜要素還元から統合的思考へ〜
パーパスというのは、ミッション・ビジョンと同義ですか?
AKI ほぼ同じなのですが、ミッションの原義が神(外側)から与えられた使命というニュアンスがあるのに対して、パーパスというのは、自分たちの内から溢れる想いを自らの存在意義とする、という意味合いが強いと思います。Knowledge Baseの場合で言えば、経営陣が発した「知的好奇心が起点となる」「楽しみながら仕事をする」といったキーワードは、自分たちはこうありたいというまさに内発的な言葉であって、Knowledge Baseらしいキーワードが出揃ってきたなという印象を持っています。
モヤモヤとした混沌の中から文脈を探る
一方、佐々木さんたちはこうした創発的アプローチの試みは初めてなので、途中で、何をしたらいいのかわからない、ちょっとモヤモヤするとおっしゃっていたことがありましたね。
AKI 創発というのは、けっして一筋縄ではいきませんからね。そこで、少し前のセッションでは、創発的なアプローチの本質部分を、理論的な背景も含めて彼らにお話させていただいたわけですね。このなかで、理論物理学者であり、対話の新たな概念を拓いたデヴィット・ボームの言葉※1を引用するとともに、サム・カナーの図(図3)を見ていただきました。この図にあるように、創発というのは、テーマに対して対話を重ねて発散した後、「GROAN(うめき声)ゾーン」とも呼ばれる修羅場=混沌とした状況をくぐり抜けて創発へ至るものです。つまり、創発とはそもそもモヤモヤしがちである、という特性を理解してもらったかと思います。
ここで重要なのは、ロジックを超えたもの――僕自身は「文脈」と言っていますが、その文脈をうまく使いながら創発へ結びつけていくことです。つまり、頭で考えたことを超えて、それぞれの想いのたけを出し合い、そこで交わされた言葉の断片からていねいに文脈を紡いでいくことで、互いに納得感やワクワク感のある方向性を生み出していくプロセスが重要なのです。
Sam Kaner「参加のダイヤモンドモデル」

- 図3 サム・カナーの「参加のダイヤモンドモデル」
もっと言うと、新たな価値づくりにロジックはとても重要な役割を果たしますが、単純な目に見える一対一の因果論理だけでなく、目に見えにくいものも含め、複雑に関係し合い、成り立っているまだ見ぬ全体像を探っていくプロセスが大事になってきます。
たとえば、経営チームによる組織のありたい姿の対話の中で、坂本さんからは「情報の編集によって知の力を解き放つ」、俊也さんからは「世の中になかったコンテンツデリバリーの方法を生み出す」、皓也さんからは「自分たちが楽しいと思うことをやる」と、一見バラバラなものが出てきました。さらに話を進めながら折り合ったのが、「知的好奇心の先の“それ、いいね!”をつきつめる」という文脈でした。
※1 デヴィット・ボーム
理論物理学者であり、かつ対話の新たな概念を拓いたデヴィット・ボームも、対話に不可欠な条件の一つとして、ファシリテーターの存在を挙げています。彼によれば、対話での集団による思考は「水面を漂い、岸に打ち上げられる草木の葉のようなもの」であり、大事なことは葉っぱに惑わされず「岸と岸の間を流れる水の流れ」である文脈を見落とさないことだとしています。言い換えれば、対話から生成される「意味の流れ」をしっかり把握することです。
野口正明著『組織の未来をひらく創発ワークショップ』(経団連)より
次なる取り組みは、パーパスから物語り(戦略)
この4象限を回していくというやり方は、AKIさん独自のものなのでしょうか?
AKI これは独自のものではなくて、ケン・ウィルバーの『万物の歴史』(春秋社/1996年)のなかで示された「ホロンの4つの象限」がベースになっています。ケン・ウィルバーは現代でもっとも包括的な思想家と言われていますが、実は前回ご紹介したティール組織において、色分けによって組織の発達段階を示すという考え方も、もとはケン・ウィルバーのインテグラル理論※2がベースになっているんですよ。
この4象限にもとづいて、まずは内面の意思的なもの、つまり、この組織を通じて私たちは誰のどのような願いや悩みをこんな風に解決したいという想いをパーパスとして言葉にします。次に、パーパスを実現するための基本方針としての物語り(戦略)に展開します。戦略というのは外的な世界、つまり目に見える世界であり、パーパスを戦略につなげていくためには明確なロジックが必要になります。ここでは、古今東西の戦略論をうまく活用しつつ、実行可能なカタチに落とし込んでいくことになる。そこをお手伝いするのが、次なる僕の役割になるわけですね。
これまでのコンサルティングでは、アンバー(順応型組織)からオレンジ(達成型組織)への移行段階での支援が多く、そこにグリーン(多元型組織)的味付けもしながらかかわってきました。が、今回のKnowledge Baseはオレンジ(達成型組織)、もしくはグリーン(多元型組織)からティール(進化型組織)へという段階なので、戦略策定に関しても、これまでとは異なる新たなプロセスが必要だろうと思っています。つまり従来のやり方では通用しないということ。そこは僕自身もさらに気を引き締めて、楽しみながら臨みたいと思っています。
※2 インテグラル理論
人間や組織、社会など、世界のさまざまな現象を包括的かつ統合的に捉えようとする理論。4象限のフレームワークを活用し、発達のレベルを組み合わせて考察することで、万物の理論の創出を試みている。
(取材・文=田井中麻都佳)